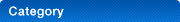130曲以上のエッセンスが詰め込まれているビートルズの『LOVE 』
レコード・コレクターズ 編集長
■企画アルバム「LOVE」制作の背景
ザ・ビートルズ(The Beatles)の「新作」アルバムと銘打たれたCD『LOVE』の余波が続いている。
「新作」といってもすでに二人のメンバー(ジョン・レノン、ジョージ・ハリスン)が他界しているビートルズが奇跡的な再結成を果たして新たなレコーディング作品を発表したというようなことでなく、これはもともと“サーカス”集団シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマンスのBGM用に企画された作品で、彼らが60年代に録音したマテリアルを、別々の曲を合体したりメドレー形式でつなげたりして再構成して聞かせるものだ。
シームレスで繋げられた約79分間。それが新鮮に聞こえるような様々な仕掛けは凝らされているが、そこからビートルズの全く未知の「音楽」が聞こえてくるわけではない。
ひとつのトラックにつき、合体のために2から3曲が一度に表記されるということはあるが、1曲の例外を除いて、全く新しい曲名が表記されているわけでもない。
合体の中で最も鮮烈な印象を残すのが、「トゥモロウ・ネヴァー・ノウズ」と、「ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー」の組み合わせだ。 実際にこの2曲の合体を最初に試してみて、それがポール・マッカートニー、リンゴ・スターの二人をはじめ、ジョン、ジョージ・ハリスンの未亡人であるヨーコ・オノ、オリヴィアやアップルのスタッフらからOKが出たことで、この大胆不敵な企画がスタートしたのだという。

■再認識させられたビートルズ音楽の奥深さ
この2曲の合体の成功の要因は、音楽的には、この2曲が共にインド音楽の、とりわけドローン(通奏低音)を活かした楽曲構造を持っていたことにある。それをよりロック的なサウンドで表現していたのが「トゥモロー・ネヴァー・ノウズ」であり、逆に、よりインド音楽そのものに近いスタイルで表現していたのが「ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー」だった。
「トゥモロウ…」はジョン、「ウィズイン・ユー…」はジョージ・ハリスンと、作曲者が違っていたというのも面白い。特にジョージの「ウィズイン・ユー…」は、ビートルズの全楽曲の中でも、最も民俗音楽的なスタイルにより接近したサウンドを持っていたところから、ポップ音楽の聞き手には少しとっつきにくい印象があったのも確かだ。
それが、同じ「ルーツ」を持ちながら、よりロック的なアプローチで表現された「トゥモロウ…」と合体されることで、ジョージ・ハリスンの意欲的な試みに新しい光が当てられることになっている。 また、ビートルズの違うメンバーにより、近い時期に別々に作られた曲が、相互に文字通り“響き合う”ような感覚を持っていたことも教えてくれる。
この2曲の合体だけをとっても、ビートルズの音楽の奥の深さを再確認させてくれるような非常に興味深い構造を持っているわけである。
■親から子へ プロデューサーの新たなる感性
そんな凄いことを、同じようなキー(音の高さ)、テンポの曲であるところに目をつけ、重ねてみたら面白いのではないかと思って試してみた、と言い切る素晴らしいセンスを見せてくれたのが、かつてのビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーティンの息子ジャイルズだった。
『ラヴ』は、クレジット上ではジョージとジャイルズのマーティン親子の共同プロデュースということになっているが、実作業を主に担当したのは息子で、まだ37歳のジャイルズだ。
父親がビートルズと共同作業を行なっていたかつての現場を知らない彼が、父のサポートを受けながらも新しい感性で取り組んだところに、このアルバムの新鮮な勢いが生まれたのは間違いない。
ジャイルズの若い感性が、ビートルズの曲のルーツを掘りあてた例は他にもある。「アイ・アム・ザ・ウォルラス」の前に緊急車両のサイレンの音が配されているが、ビートルズに詳しい倉本美津留さんによれば、この曲「アイ・アム・ザ・ウォルラス」のイントロこそは、ジョンがそうしたサイレンの音をモチーフに作ったものなのだそうだ。
ジャイルズはそのことを知らずに自然な流れでサイレンの音を挿入したという。まさに感性の勝利だ。
さらに、ポール作の「レディ・マドンナ」と同時期のジョン作の曲「ヘイ・ブルドッグ」のリフが合体されて美しくも刺激的なハーモニーを奏でてしまう部分には、かつてジョンが作曲した曲の未完成部分をポールが作曲した曲でピッタリと埋めて大作「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」が完成したという、かつての美しいエピソードに時空を超えて繋がるような何かが確かにある。
■再構成アルバムは音楽業界にとって光明なのか?
トラックごとの再構成の妙を語っていこうと思うと、このスペースでは到底無理。それほど細かい作業の積み重ねでこのアルバムは出来上がっている。 収録トラック数は26に過ぎないが、一説によれば、ここにはビートルズの130曲以上の“エッセンス”が詰め込まれているのだそうで、すでにマニア間では、それらをどこまで解明できるのか?という競争的な状況も生まれているようだ。
音楽作品としてリリースされた『ラヴ』が一種のゲームソフトのような役割さえ果たしてしまっているというのは、極めて21世紀的状況なのかもしれない。 しかし、『ラヴ』を巡るこうした状況を興味深く眺めながらも、僕の中には、ちょっとした危惧も生まれつつある。
それは、この作品が、レコード会社の内で過去のカタログ音源の出し直し=リイシューを担当するセクションにとって、リマスター、紙ジャケなどに続く、新たなビジネスモデルの誕生!と捉えられてしまうのではないか?というものだ。
『アビー・ロード』の(LPではB面に収録されていた)メドレーや、二つのレコーディング・テイクを合体してひとつの作品に仕上げた「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」のエピソードを思い起こしていただければわかるように、ビートルズの場合は、自分たちの生演奏を素材に、ジョージ・マーティンのディレクションの下、かなり大胆に再構成しながら作品を作っていったという歴史がある。
もちろんそうした手法は、その後のアーティストたちにも受け継がれていったわけだが、ビートルズの場合は、先駆者ならではの大胆さ、ギクシャクした感覚まで含めて個性になっていたようなところがあった。 「愛こそはすべて」だって、もともとグレン・ミラーの「イン・ザ・ムード」やビートルズ自身の「シー・ラヴ・ズ・ユー」といった曲の断片が大胆に重ねられた作品だった。
つまり、ビートルズの場合は、60年代当時の制作方法自体に、『ラヴ』に通じるようなものがもともとあったのである。そうしたもともとの音楽的特徴にプラスして、プロデューサーの“世襲”の成功という要素もあった。
もし他アーティストでこうした再構成アルバムを作ろうとしても、これだけの好条件が揃うのかどうか?は怪しい。そこを慎重に考えず、『ラヴ』に続けとばかりに安易な再構成アルバムが次々に粗製濫造されるような状況だけは見たくない。
- いただいたトラックバックは、編集部が内容を確認した上で掲載いたしますので、多少、時間がかかる場合があることをご了承ください。
記事と全く関連性のないもの、明らかな誹謗中傷とおぼしきもの等につきましては掲載いたしません。公序良俗に反するサイトからの発信と判断された場合も同様です。 - 本文中でトラックバック先記事のURLを記載していないブログからのトラックバックは無効とさせていただきます。トラックバックをされる際は、必ず該当のMediaSabor記事URLをエントリー中にご記載ください。
- 外部からアクセスできない企業内ネットワークのイントラネット内などからのトラックバックは禁止とします。
- トラックバックとして表示されている文章及び、リンクされているWebページは、この記事にリンクしている第三者が作成したものです。
内容や安全性について株式会社メディアサボールでは一切の責任を負いませんのでご了承ください。