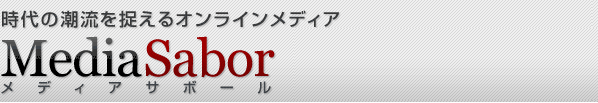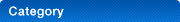ロサンゼルスのエコ上級者向け媒体「Whole Life Times」を通して、ライフスタイルを見直してみる。
- 米国在住ジャーナリスト
2年前に発行されはじめたロサンゼルス発のグリーンマーケット向けフリーマガジン「Whole Life Times」。通称WLT。A Conscious Enlightenment Publication社発行の同媒体は、すべて記事の内容に限らず、印刷においても、排水を利用して再生産された再生紙に、Soyインクを使用。さらに配達に使われる車もハイブリッドより電気自動車で、というこだわり。
また媒体の記事の再利用も活発だ。A Conscious Enlightenment Publication社が他に発行する「Yogamates」、シカゴとシアトルでそれぞれ発行されている「Conscious Choice」、およびサンフランシスコの「Common Ground」と、他の4つの媒体でも、それぞれの編集者の目に留まれば、記事が転用されることもある。ちなみにそれぞれの媒体は独立しており、編集長以下各エリアに根ざしたスタッフが、媒体作りを行っている。内容はキャッチーというよりも、むしろしっかりと書かれた読み込みが必要な記事が多く、また学術書とまではいかないものの、専門用語も大量に使われる読み物が多い。
ロサンゼルスは西海岸のグリーン/オーガニックのマーケットにとっては、非常に洗練され、啓蒙された人々が多く住む場所。その分重要視されているが、一方で、資本至上主義にどっぷり漬かりきっている人もまだまだ多い。とはいえ、最近のメディアの煽りも受けて、少しずつ環境問題に興味を持つ一般人が増えてきた。しかし、同時に商業主義がグリーンマーケットにも蔓延してきてしまっていることも事実なのだ。そんな状況を迎えている現在、WLTで今月特集されていた内容が下記である。
「スピンサイクル:本物のエコか、それともエコかぶれのものか?」
http://wholelifetimes.com/2008/04/spincycle0804.html
今日メディアを通じて<環境保護>を助長するためのHow-toとして、
沢山の情報が投げ込まれている。例えば<小さな蛍光灯が、北極熊を守る!>
<バンブー素材(竹)の服は環境とファッションのより良い関係性を構築する>
<ミネラルメイクは顔を可愛くするだけなく、地球にも優しい!>など。
だが実際は、CFL電球は未だに神経毒が入っているし、バンブー素材の服は
発癌性物質が含まれている。またミネラル化粧品で肺気腫になる可能性が十分
あるのだ。どうやってこの偽善から身を遠ざけられるだろうか?
このキャッチだけでも、かなりの衝撃的な事実が隠されている。特にファッション業界と密接な関わりを持つ私は、以前から「バンブー(竹)」素材のアパレル製品は、実はまったくエコフレンドリーではない、ということを耳にしていたが、あらためて「発癌性」というキーワードを見てどきっとした。ちなみに「オーガニックコットン」もしかりで、例えオーガニックコットンのTシャツであっても、その上に通常の化学染料のインクでプリントをしたら、それはまったくの非エコフレンドリーTシャツなのである。また、生産の過程で環境を考慮した工場で縫製されているかなど、せっかくのバンブー商品でも、「非エコフレンドリー」になる可能性は山ほどあるのだ。
車についても、同記事の中では2007年のLAオートショーで「最もエコフレンドリーな車」として選ばれたChevy Tahoeのハイブリッド車に対して、環境学者たちからどよめきがあった、と指摘している。彼らからすれば、1ガロンであの巨大なSUVが20マイルも走れる事実自体、何の魅力もなく、むしろなんて無駄な労力をかけて作ったのか、と感じているというのだ。環境のことを考えれば、ガソリンを使わずに済む、徒歩や自転車がどれほどすばらしく、また公共の移動手段を上手に使うほうがずっと重要だと指摘している。
こうした記事は、現時点で環境に非常に配慮した人達が、エコロジーの「ブーム化」を恐れているという証拠だ。そしてブームに乗ってしまったであろう一般人からすると、彼らは「偽エコロジスタ」を排除しようとしているのではないか、と感じてしまうのは私だけだろうか。
私はビン、缶はもとより、リサイクルできるものはきちんと分別しているし、ファーマーズ・マーケットで地元新鮮野菜を手にすることも好きだし、パタゴニアやアメリカン・アパレルの企業理念に共鳴する。だが一方で、車の代わりに職場へ自転車や公共交通手段で通っているわけでもないし、欲しいものは購入して、不要なものはやはりゴミに出す。すべての食べ物で、オーガニックのものを選べているわけでもないし、服だって、未だに中国製の安いドレスも買ってしまうし、ミネラルのメークセットも持っている。
つまり環境に関する知識が中または下レベルで、本当に真剣に地球に配慮しきれていない私にとって、この記事で自分の行動に完全に「ダメだし」されてしまったように感じてしまった。もちろん、私を含め「ちょっとだけエコロジスタ」な人からすると、こういう記事を通して学習し、知識を得るに違いないのだが、一方でエコ生活をストイックに実践している人と、非常に距離を感じてしまった瞬間でもあるのだ。
こうした中で同じ媒体から見つけた別の記事を読んで、少しほっとした。記事に登場する場所を訪れれば、私みたいなエコロジスタ初心者が最初に一歩を踏み出すいいきっかけがつかめるかもしれない。
「Whole Life Times」よりhttp://wholelifetimes.com/2008/04/oor_venice0804.html
ヴェニスビーチにサステナブルコテージがオープン!1920年代の荒れ果てた古い海辺の
バンガローを、2人の起業家が見事に蘇らせた。アーティストのシンシア・フォスターと
環境経済学者のカレル・サムソンは、3軒続きの小さなコテージを、
オーガニック・インテリア・デザインの巨匠、ケリー・ラプランテ
(http://www.organicinteriordesign.com/)の手も借りて、一棟ごとユニークな
名前と独特のインテリアを備えたビーチハウスに仕立て上げたのだ。3軒に共通する
ことといえば、オーガニックのリネンとマットレス、水周りはすべて浄水、
非VOC(揮発性有機化合物)製品、またエネルギーを有効利用した電気製品と
再利用品の家具で満たされていること。「今私たちは小さい建物をみつけると
別の見方をしていて、何か私達にできることはないかと考えてしまうんです」
というフォスター。またいつか挑戦したいそうだ。
Venice Beach Eco Cottage(http://venicebeachecocottages.com/)
バケーションハウスでエコ体験というのも、なんだか素敵だし、一石二鳥っていう気分だ。もちろんエコ上級者にとっては、隅々まで配慮されたバンガローはロサンゼルスエリアの憩いの場になるに違いない。こうしてみると、あまり肩に力をいれずに、一歩ずつできることをやってみるくらいのスタンスで、取り組むくらいでいいのではないかと思う。結果が目の前に現れないのに、あまりにも毎日の小さな努力をしすぎて、息切れしてしまわないように、やれることをこつこつと。そして新しい情報や知識が入ったときは、きちんと次の情報に頭を切り替え従う。それがこの環境問題とやらと付き合うには必要そうだ。
【編集部ピックアップ関連情報】
○負け犬の矜持 2007/10/27
「Cultural Creatives (生活創造者)に見る、モラルの経済」
ロハス(LOHAS:Lifestyles Of Health And Sustainability)の提唱者、
米国の社会学者ポール・レイ氏と心理学者シェリー・アンダーソン氏は、
1986年から15年間にわたり15万人を対象に調査をした結果、全米の大人の
26%(5000万人)が、ある明確な志向を持った層であることを発見。それは、
40年前にはほとんど見られなかった新しい価値観、世界観、ライフスタイル
だった。そして、この人々を「カルチュラル・クリエイティブス(生活創造者)」
と呼び、LOHASの中心層であると位置付けた。
http://happyoptimist.typepad.jp/blog/2007/10/cultural_creati_7007.html
○松岡正剛の千夜千冊 2002/10/16
『消費社会の神話と構造』ジャン・ボードリヤール
本書ではそこのところを、こう書いている、「事態はもっと深刻である。
システムは自分が生き残るための条件しか認識しようとせず、社会と個人の
内容については何も知らないのだ」「ということは、どこにも消費
システムの安定化は不可能だということなのである」というふうに。
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0639.html
○雲の平 で <DRC> 2007/03/08
「ジャン・ボードリヤール氏 Jean Baudrillard 没」
私の卒業論文のテーマは、日本の 「消費社会」 を扱ったもの。
内容は、この人の著書 『消費社会の神話と構造 1979年』 の、
「家庭電化製品や衣料、車といった各種の商品は、その使用価値だけで
用いられるのではなく、社会的権威や幸福感といった他人との差異を示す
「記号」として現われる。」 という分析の 「差異」 化が、日本に
おいては、「同列化」 「隣よりちょっと上」化 という形で表れ、
「一億総中流」 意識が生まれるという推論を組み立て、それに
肉付けしたもの。
http://kumonotairadedrc.blog28.fc2.com/blog-entry-95.html
○サラリーマン空手日記「ジャン・ボードリヤール」2007/09/07
消費社会について批判的に書いてある著作を読んでおいた方がいい
時代だと紹介されていたのが「象徴交換と死」(ちくま学芸文庫)と
「消費社会の神話と構造」(紀伊国屋書店)だった。
http://blog.livedoor.jp/go_sabaki/archives/50769369.html
- いただいたトラックバックは、編集部が内容を確認した上で掲載いたしますので、多少、時間がかかる場合があることをご了承ください。
記事と全く関連性のないもの、明らかな誹謗中傷とおぼしきもの等につきましては掲載いたしません。公序良俗に反するサイトからの発信と判断された場合も同様です。 - 本文中でトラックバック先記事のURLを記載していないブログからのトラックバックは無効とさせていただきます。トラックバックをされる際は、必ず該当のMediaSabor記事URLをエントリー中にご記載ください。
- 外部からアクセスできない企業内ネットワークのイントラネット内などからのトラックバックは禁止とします。
- トラックバックとして表示されている文章及び、リンクされているWebページは、この記事にリンクしている第三者が作成したものです。
内容や安全性について株式会社メディアサボールでは一切の責任を負いませんのでご了承ください。