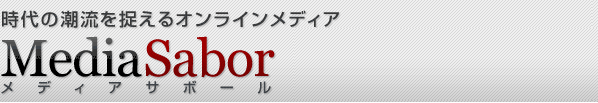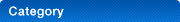美術館がtwitterアカウントを運用することで生活にアートがやってくる
- ライター/ブロガー
twitterの勢いが止まりません。ワールドワイドでのデータですがTwitter、6月の全世界ユーザー数は4450万人に達したそうです。
私はアート関連が昔から好きなので、自分で展覧会やギャラリーなどにできるだけ行くようにしているのですが、展覧会と日々の行動ということで考えるとボトルネックになることが3つあります。
・ネームバリューのない展覧会は情報がメディアに流れない
・展覧会の開催そのものを知らない
・展覧会の会期を忘れて、行き損ねる
で、こういうボトルネックを解決するのに、現状の最適解がtwitterなのです。
アメリカでは、MOMAと大きな美術館がtwitterアカウントを運用したことがニュースになりました。
MuseumModernArt
http://twitter.com/MuseumModernArt
MOMAがtwitterをはじめたわけ(http://blog.kosukefujitaka.com/2009/05/momatwitter.html)。
担当者が勝手にはじめてしまったというのは、実にアメリカの美術館らしいです。
ということで、アメリカではどんどん他の美術館もtwitterをはじめています。
brooklynmuseum
http://twitter.com/brooklynmuseum
philamuseum
http://twitter.com/philamuseum
アメリカの美術館に行くと、とても感心するのは、アメリカでは美術館というのはパブリックでオープンなスペースと認知され、美術館側もそう考えているということです。
http://www.philamuseum.org/calendarEvents/
そのせいもあるのでしょう。日本の美術館ではいわゆる期間限定の特別展みたいなものが集客の中心ですが、アメリカでは常設展や日々行われている多種多様なイベントが集客の中心と、人の流れもかなり違います。
日本ではNHKの新日曜美術館のアートシーンに紹介されないと集客できないみたいな話もあるぐらいに、まだまだアート関連の情報が人々のところに届いていません。
ということで、このアート系の情報では孤軍奮闘しているともいえるのが「tokyoartbeat」(http://www.tokyoartbeat.com/)。
もちろん、twitterアカウントも運用しています(http://twitter.com/TokyoArtBeat_JP)。
ただ、日本でもアートのオープン化の動きは進んでいます。アートフェスティバルとして定着してきた感のある「越後妻有アートフェスティバル」では寄付を作家へのサポートというような形で運営しています(http://www.echigo-tsumari.net/donation/index.html)。
ということで、やはりtwitterという新しいプラットフォームはやはりネット本来の魅力である「オープンであることが価値を生む」というところにおいて、今もっともいい流れを生み出しているサービスと言っていいのではないかと思います。
【関連リンク】
http://blog.kosukefujitaka.com/2009/01/twitter.html
- いただいたトラックバックは、編集部が内容を確認した上で掲載いたしますので、多少、時間がかかる場合があることをご了承ください。
記事と全く関連性のないもの、明らかな誹謗中傷とおぼしきもの等につきましては掲載いたしません。公序良俗に反するサイトからの発信と判断された場合も同様です。 - 本文中でトラックバック先記事のURLを記載していないブログからのトラックバックは無効とさせていただきます。トラックバックをされる際は、必ず該当のMediaSabor記事URLをエントリー中にご記載ください。
- 外部からアクセスできない企業内ネットワークのイントラネット内などからのトラックバックは禁止とします。
- トラックバックとして表示されている文章及び、リンクされているWebページは、この記事にリンクしている第三者が作成したものです。
内容や安全性について株式会社メディアサボールでは一切の責任を負いませんのでご了承ください。